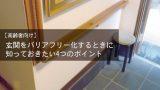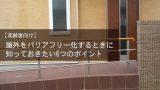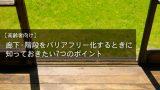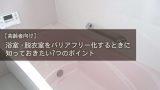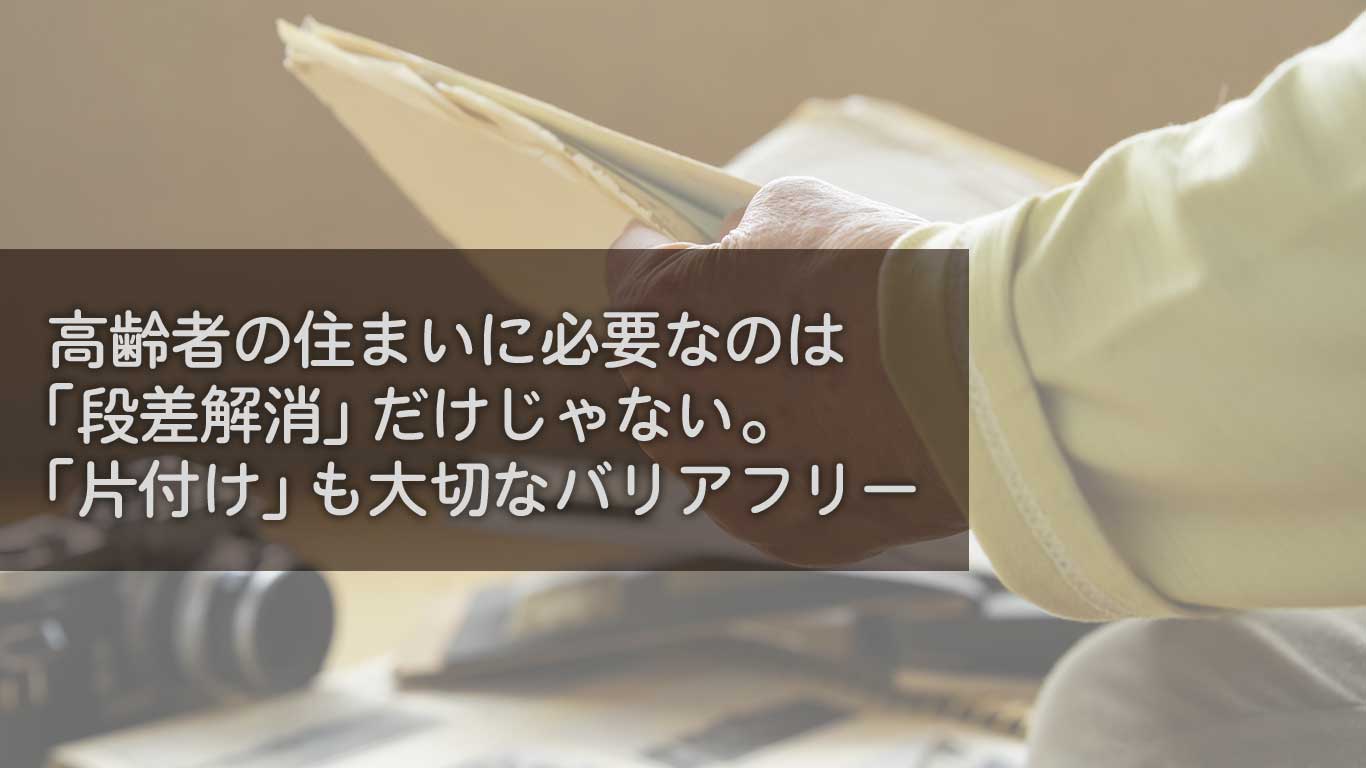高齢のご家族の住まいを整える上で、「バリアフリーにした方がいいかな?」と考えたことはありませんか?
段差をなくしたり、手すりをつけたりといったバリアフリーリフォームはよく知られていますが、まずは片付けから始めるのが本当の「バリアフリー」かもしれません。
足元に置かれた荷物につまづいたり、必要なモノがすぐに見つからずに無理な姿勢になったり。
こうした「モノのバリア」は見落とされがちですが、移動の妨げや転倒、ケガの原因になることも少なくありません。
「久しぶりに実家に帰ったら、なんだか物が増えてる…?」
「昔は綺麗好きだったのに、なんで片付けなくなったんだろう?」
そう思って「片付けてね」と言ってみても、なかなか行動に移さなくてイライラしてしまうこともあります。
怒って関係を悪くしてしまう前に、高齢者にとって「片付ける」「捨てる」という事が、そう簡単ではないということをぜひ知ってください。
体力的にも、気持ちの面でも、若い頃とは違う難しさがあるのです。
ここからは、片付けに悩むご家族の視点に寄り添いながら、「見えづらいバリアフリー」としての「片付け」について、わかりやすく説明していきます。
関連記事 高齢者向けのバリアフリーリフォームを知りたい方は以下のリンクからご覧ください。
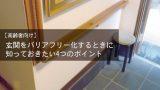


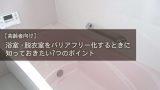
段差だけじゃない!バリアフリーには「片付け」も大切なんです

バリアフリーというと、「段差をスロープにする」「手すり設置する」など、工事をイメージされる方が多いのではないでしょうか。
もちろん、それは高齢者の生活を支える大切な要素です。
でも実際の暮らしの中では、段差よりも「モノ」が暮らしにくさや、ケガの原因になっていることも多くあります。
- 通路に置いたダンボールにつまづいた
- 足元にある新聞紙や衣類を踏んで転びそうになった
- 押し入れや引き出しからモノを探すために無理な姿勢になった
- 積み上げていたモノが崩れてきて、頭をぶつけた
- そもそもモノが多すぎて、生活するスペースが圧迫されてしまっている
こうしたことは、どこのご家庭でも起こりうる「あるある」です。
親の暮らしが心配になることは自然なことですが、深刻に悩みすぎなくても大丈夫。
同じように感じている方はたくさんいますし、少しずつ見直していくことで、ちゃんと安全な環境に近づけます。
とはいえ、「片付いていないこと」が原因で起こる「見えないバリア」によって、生活上の支障が出てくることも事実です。
- 必要なモノが見つからない
- 本人や介助者、訪問サービスのスタッフが動きにくい
- 認知症の方にとって、混乱や不安の原因になってしまっている
そんな状況になってきたら、住まいを見直す合図かもしれません。
「片付け」は見た目の美しさのためでだけのものではありません。安心して安全に暮らすための「もう一つのバリアフリー」なのです。
誰かに勧められたリフォーム工事をする前に、まずは家の中のモノを適切に管理する方法から考えてみることが、高齢のご家族の暮らしを守る第一歩になります。
高齢の親にとって“手放す”のは大変

上で述べたように、高齢の方にとって「モノを捨てる」「手放す」というのは、私たちが思う以上に難しいことです。
戦時中やモノのない時代を経験した世代であることから、ものを捨てることに抵抗がある方も多く、「もったいない」「いつか使うかも」といった気持ちはとても自然な感情です。
さらに年齢を重ねると判断力や気力が落ちてくることもあり、「捨てる」「残す」の判断そのものが、「心の負担」になってしまうこともあります。
そんな時こそ大切なのは「気持ちの整理」に寄り添うこと。
「これはどんな思い出があるの?」
「今の生活で本当に必要かな?」
といった会話を通して、少しずつ心の準備が整っていきます。
大切なのは捨てることではなく、安心して暮らせる環境を作ることです。親の思いに寄り添いながら、少しずつ住まいを整えていく事が大切です。
そして、忘れてはならないのが、片付けが進まない理由は「気持ち」だけではないということ。
加齢による身体の変化も、片づけを難しくしている原因の一つです。
次はその、加齢による身体の変化について、詳しく説明していきます。
足腰の衰えや視力の変化も…片付けが進まない身体の理由

片付けが進まないのは「やる気がないから」ではありません。
前述の通り、高齢になると身体や認知の機能が少しずつ低下し、それが片付けにくさにつながっている事がよくあります。
身体機能の低下による困難
■足腰が弱くなり、しゃがんだり立ち上がったりがつらい
→床にあるものを拾ったり、低い棚に収納する動作が難しくなります。
■高いところに手が届かない
→身体の可動域が狭まり、天袋や押入れ上段、つり戸棚の整理ができず、モノがたまりがちになります。
■視力が落ちて、細かいものやゴミが見えにくい
→ゴミや汚れに気づけず、片付けの必要性を認識しにくくなります。
■握力や指先の力が弱くなり、引き出しや箱が開けにくい
→開閉が億劫になり、中身の整理や確認が難しくなることがあります。
認知機能・判断力の低下による影響

■ゴミかゴミではないか、必要か必要ではないかの判断が難しくなる
→判断を先延ばしにしてしまったり、迷ったままモノを保留し続ける傾向があります。
■どこにしまったか忘れたり、既に持っていたけれど忘れてしまって何個も買ってしまったりしてしまう
→同じものを何度も買ってしまったり、閉まった場所がわからずに出しっぱなしになってしまったりします。
こうした状態になると、家の中にモノが増えやすくなり「片づけよう」と思っても、どこから手を付けていいかわからないという状況に陥りがちです。
片付けを手伝う時は「散らかっている=怠けている」ではなく、身体や認知機能の変化によって難しくなっている可能性があることを前提に接することがとても大切です。
「やってあげる」ではなく、「できない理由を取り除いていく」という姿勢こそが、無理なく片付けを始めるための一歩になります。
気持ちに寄り添って。片付けのハードルを下げるコツ
ここまでで、高齢になると片付けが難しくなる理由を「心」と「身体」の両面からお伝えしてきました。
「なるほど、理由はわかった。それで、何から始めよう?」
と疑問を持った方のために、ここからは心のハードルを下げて、無理なく始められる片付けのコツをご紹介します。
まずはコミュニケーションから始めよう

片付けは、作業そのものより「人との関係性」が鍵になります。
- まめに連絡して、普段から関係を保つ
- 親のペースに合わせて、ゆっくり進める
- 1日5分、1か所だけなど、短時間・小さな範囲から始める
- 「心配しているから」と「安全のため」であることを伝える
「片づけさせる」のではなく、「一緒にやろう」という姿勢が安心感につながります。
気力や体力に合わせて、まずは短時間から。
片づけた実感の大きいキッチンのつり戸棚や下駄箱などや、モノが多すぎて安全性に不安のある場所がおすすめです。
手元に残すと決めたものは、もともとしまっていた場所より大きく変えないことがいいでしょう。場所を変えてしまうと、片づけた場所を忘れてしまって、かえって探せない状況になってしまうことがあります。
どうしてもモノを手放せないときは

モノを捨てることに抵抗がある場合は、無理に捨てる必要はありません。
整理の第一歩として、気持ちの折り合いをつける工夫をしてみましょう
- 写真を撮って記録に残す
- 「迷ったら一時保管(手放す条件も決めておく)」をルールにする
- 服や道具は実際に着たり使ったりして、本当に必要か再確認する
- 使えるからもったいないは、代わりにリサイクルショップに持ち込んだり人にあげたりする
- 傷みや壊れている部分を見つけて、「これはもう十分使ったね」と伝える
- ゴミ出しや粗大ゴミの手配を代行する
こうした方法で、モノよりも「気持ちの整理」を重視したアプローチをしていきましょう。
手伝う側の判断基準は「危なくないかどうか」

片付けというと「きれいに整った部屋」を目指したくなりますが、高齢者の片付けで大切なのは「キレイ」より「安全」です。
- 動線をふさいでいないか
- 足元にモノが落ちていないか
- 頭上に崩れそうな荷物がないか
- 無理のない姿勢で出し入れができるか
まずはこうした「危ない場所」から少しずつ整えていきましょう。
多少の出しっぱなしはOK。大切なのは「その人らしく安全に暮らせる空間」を整えることです。普段の生活リズムで一時的に置く場合があるなら、それを尊重する方が良いでしょう。大きく生活動線を変えないよう調整をします。
また、モノを一気に減らしすぎると、喪失感から次の片付けが億劫になることがあります。
「無理に捨てなくていい」「気持ちに合わせて進めていけばいい」と伝えることで、安心して片付けに向き合えるようになります。
無理なく始める!片付け3ステップで安心空間に

片付けを進めるには「1.整理する(見直す)」→「2.減らす」→「3.しまう(収納する)」の基本の3ステップで進めていきます。
すでに、「1.整理する(見直す)」「2.減らす」コツはお伝えしてきました。ここからは、改めて2つのステップをまとめつつ、「3.しまう(収納する」のステップを説明してきます。
片付けに関する書籍も多く出版されているので、そちらも参考にしながら自分に合った方法を見つけるのもよいでしょう。
step1. 整理する(見直す)
まずは、その場所にあるものをすべて出すことから始めます。
一度出して「何があるか」を目で見て把握しましょう。モノの整理より、頭や心の整理を優先します。
出したものから「残すもの」「残さないもの」「保留にするもの」を、ここまでで説明した方法で整理していきます。
step2. 減らす
整理ができたら、行動に移します。
減らす方法にもいくつかあり、捨てる・リサイクルショップなどに持ち込む・人に譲るなどがあります。
「捨てる」ことに抵抗がある方も、誰か必要な人の手に渡る場合なら、抵抗なく減らすことができる場合があります。様子を見ながら、ちょうどいい方法を探っていきます。
粗大ゴミの手配やリサイクルショップの持ち込み、譲る人を探すなど、気力、体力の必要な作業も多いので、このフェーズは積極的に手伝いをしてあげてください。
step3. しまう(収納する)

しまう時は、身体の動きや目の見え方、記憶力などに合わせて収納方法を工夫すること大切です。
- 収納スペースの明暗さをつけて、見やすくする
- 普段使うものは、無理のない姿勢で手を伸ばしやすい位置に(高すぎ・低すぎは避ける)
- 引き出しは軽く開け閉めできるものを選ぶ
- 「見える収納」を使い、しまう動作そのものを減らす
- しまう場所を大きく変えず、これまでの生活動線をできるだけ守る
既にお伝えした通り、高齢になると足腰の動きだけでなく、視力や記憶力にも変化がでてきます。
しまった場所がわからなくなったり、取り出すことが負担になってしまうこともあるため、「身体にやさしい収納」を意識しましょう。
何度もお伝えしていますが、大切なのは「安全に暮らせる空間」であることです。
「出しっぱなし」という生活リズムがある方なら、一時置きしていい場所を作っておくのも一つの方法になります。
自分たちだけで抱えないで。プロの手を借りるのもアリです

片づけたい気持ちはあっても、「何から手を付けたらいいかわからない」という方は少なくありません。
さらに、実家が遠かったり、仕事や育児で忙しかったりして、「一緒にやりたくても時間がとれない」というご家族も多いのではないでしょうか。
また、いざ一緒に片付けようとすると、親が嫌がったり、怒ってしまったりして、うまく進まないというケースもよくあります。
お互い感情的になってしまい、疲れてしまうことも。
そんな時は、無理に一人で抱え込まず、外部の手を借りるのも大切な選択肢です。
例えば、第三者であるプロが代わりに伝えることで、親がすんなり行動してくれることもあります。
「身内だからこそうまくいかない」という状況は、決して珍しいことではありません。
専門家は、本人の気持ちや身体状況に配慮しながら、無理のない方法で片付けをサポートしてくれます。
家族だけでは難しいと感じたら、遠慮せず、相談できる人に頼ることも前向きな一歩です。
バリアフリーというと、段差の解消や手すりの設置といった「住まいの工事」を思い浮かべがちですが、高齢の方が安心して暮らすためには、片付けも大切なバリアフリーのひとつです。
心と身体の両方の事情で、高齢の方は片付けが難しくなっている場合があります。
「どうして片づけないの?」と責めるのではなく、寄り添いながら、暮らしやすい環境を一緒に整えていくことが大切です。
住み慣れた家で、これからも安心して過ごせるように、「片付け」から始まるバリアフリーを一歩ずつ始めてみませんか?
関連記事 高齢者向けのバリアフリーリフォームを知りたい方は以下のリンクからご覧ください。